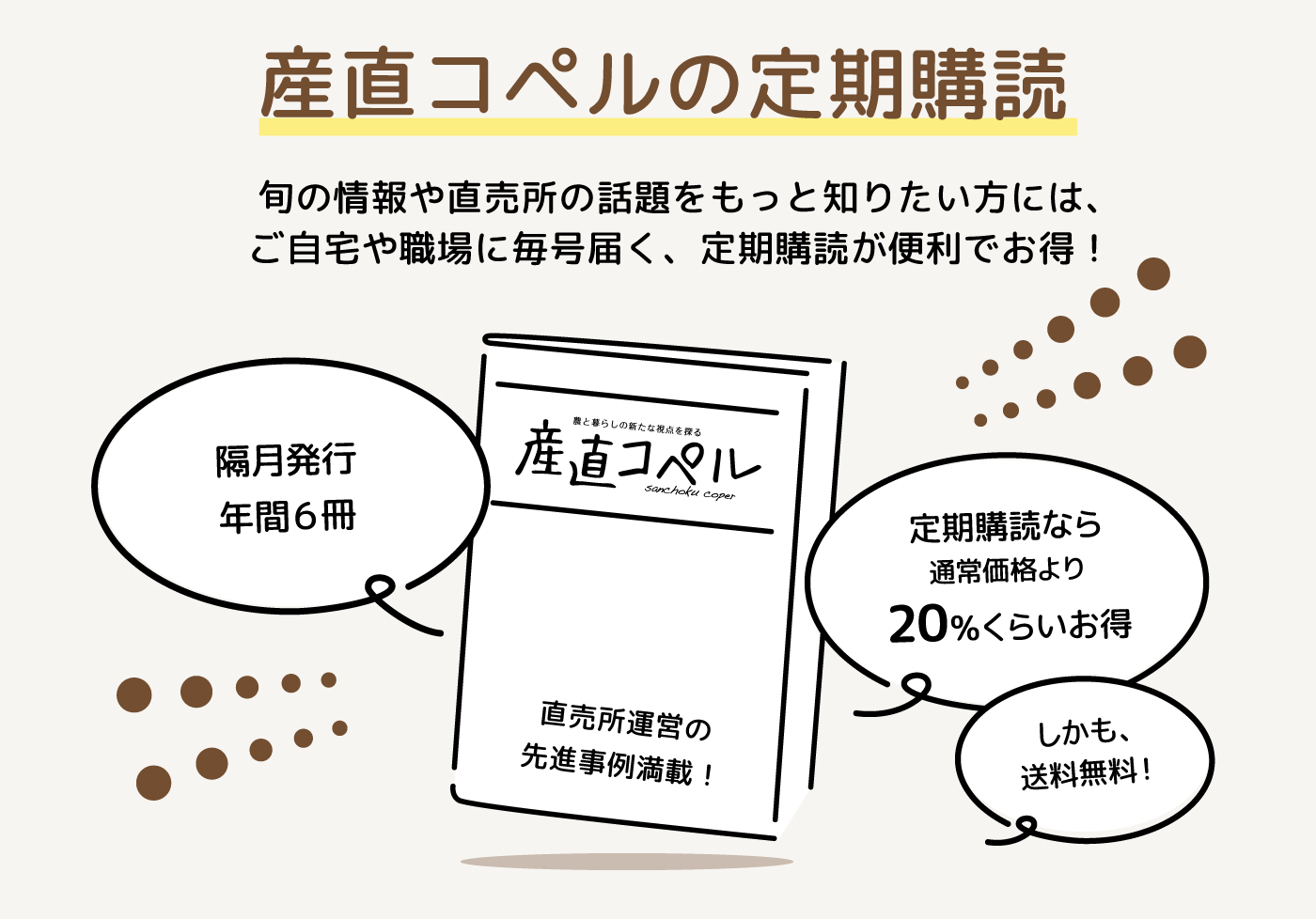シードルとは、リンゴを原料にしたお酒のことだ。多くが発泡性のタイプで、伝統的な製法ではリンゴの果皮についた天然の酵母菌を用い、リンゴ果汁を発酵させることでつくられてきた。現在は安定して醸造できる酵母菌を用いることが多い。産地として知られているのは、フランス北西部のブルターニュ地方やノルマンディー地方。シードルという呼び方もフランス語由来だ。
近年、日本産シードルも数を増やしており、リンゴの産地である長野県北部の飯綱町でも、町で栽培されたリンゴを使ったシードルがつくられている。なかでも飯綱町に伝わる和りんご「高坂りんご」を使った「いいづなシードル(ふじ・高坂りんご)」は、飯綱町でしか手に入らない知る人ぞ知る商品だ。この「いいづなシードル」を醸造するのが、同町に本社を置く(株)サンクゼール。海外から伝わったシードル文化が、いま日本独自の味わいをつくり始めている。(文・柳澤愛由)
リンゴと発酵。シードルのおいしさをつくるには

「『高坂りんご』を使ったシードルは、ここ飯綱町でなければつくれません。海外から伝わった文化ではありますが、日本にしかないものを使っていくことも私たちの使命のひとつだと考えています」。そう話すのは(株)サンクゼールの三浦秀一さん。高坂りんごを使った「いいづなシードル」を生むきっかけを作ったひとりだ。
シードルの仕込みは冬に行う。まず収穫したリンゴを皮のままクラッシュし、プレス機に入れ果汁を搾り、その果汁をタンクに入れ酵母を加えて熟成・発酵させる。ちなみに、アルコール発酵とは、酵母が糖分を分解してアルコールと二酸化炭素を生成する働きのことをいう。タンクでの一次発酵の過程で発生する炭酸ガスは空気中に放出されるため、出来上がるのは無発泡のリンゴ酒だ。一次発酵の期間は気温によって変わり、2週間のときもあれば、2カ月のときもある。出来上がったリンゴ酒に酵母と糖分を加え瓶に詰め、密閉した瓶内で二次発酵させることで、炭酸ガスが液体内に溶けていく。この瓶内二次発酵が炭酸ガスをつくり出す。その後、熱湯に浸して酵母の働きを止める。
シードルには大きく分けて甘口(スイート)・辛口(ドライ)の2種類がある。この味わいを決めるのも発酵だ。酵母の働きをどのタイミングで止めるかによって、糖の残り具合が決まる。この見極めがシードルの味わいを左右する。「ブドウに比べてリンゴはさっぱりとした味わいなので、ドライにし過ぎると物足りなさを感じる人もいます。それを補うのが、甘味とガス圧とのバランスだと考えています。サンクゼールではドライ寄りのシードルでも、甘味を少し残すよう醸造しています」(三浦さん)
ちなみにシードルの製造方法にはほかにもいくつか種類があり、どの製造方法を選択するかでも個性が分かれるそうだ。
日本のリンゴと海外のリンゴ

サンクゼールで最初にシードルを商品化したのは2002年のこと。ふじと紅玉のシードルだった。「以前、フランス人にふじで作った原酒を飲んでもらったことがあったのですが、『アルコール度数も高くてコクもあるし、すごくいいリンゴだね』と喜んでいました。ただ、同時に彼らが言っていたのは、シードルづくりには甘みのあるリンゴだけではいけない、苦みや渋み、酸味も必要で、それがシードルに面白みやバラエティを与えてくれる、ということでした」(三浦さん)
日本とフランスのシードルの違いのひとつが、シードル用リンゴの栽培方法だ。「いいづなシードル」のアルコール度数は6%だが、実は、フランスをはじめとする海外でつくられるシードルはアルコール度数4~5%とさらに低めのものが多い。日本の場合、生食用の糖度の高いリンゴがそのままシードルにも使われる。しかし海外のシードル用リンゴは、もともと糖度の低い品種が多い上、栽培においても糖度を気にせず、ほぼ自然に任せた方法でつくられている。生食にするため一つひとつの実に手をかける日本の栽培方法と比べると、かなり省力化した方法だ。
もうひとつの大きな違いは、シードルに使われるリンゴの品種の数だ。日本の場合、シードルを単一品種で醸造するケースも多い。しかし、シードルの本場であるフランスでは、〝シードル用〟に特化したさまざまなリンゴ品種が使われる。ノルマンディー地方では、甘味、酸味、苦み、渋みなど、それぞれの味わいから数種類ずつ選びブレンドしてシードルをつくらなければならない、という法律まであり、1つのシードルに対し20種類ほどのリンゴを使うという。アルコール度数はコクにもつながるため、もしフランスのような栽培方法でつくったリンゴを単品種で醸造したら、より単調な味わいになってしまう。多品種をブレンドすることで単調な味わいになるのを防ぎ、味に深みを出してきた歴史があるのだという。
日本のリンゴ栽培の技術は高い。多くの農家が、一つひとつの実に手をかけながら、まるで芸術品のような果実をつくる。そうしたリンゴでシードルをつくれば、アルコール度数も高くコクのあるものが出来上がる。しかしそこへ面白みや深みを足すには、全く別の個性が必要だ。日本でも酸味のある品種は比較的栽培されているが、生食用のリンゴが主流の日本で、〝渋み・苦み〟を持つリンゴはなかなか無い。その独特な個性を持つのが「高坂りんご」だった。
飯綱のりんご文化は「高坂りんご」から始まった

「和りんご」は平安時代に中国から伝わった植物だといわれている。直径4~5センチメートルほどの小さな実をつけ、かつては日本各地で盛んに栽培されていた。「高坂りんご」の名前の由来にもなっている飯綱町高坂地区は、江戸時代には林檎の花が咲き誇る「花の名所」として知られるようにもなっていたという。8月に収穫期を迎える高坂りんごは、お盆のお供え用としても重用され、善光寺近辺(現在の長野市)などにも流通していたと伝えられている。甘いものが少なかった時代の人々にとっては格別なご馳走でもあった。
現在日本で広く栽培されているリンゴは、明治時代にアメリカから持ち込まれたものだ。強い甘みとたっぷりとした果汁を持ち、可食部の多い西洋リンゴに、当時の日本人は目をみはったことだろう。西洋リンゴが導入されてから、和りんごは急速に姿を消していった。

「高坂りんご」も昭和の終わりには、その名を知る人すら少なくなっていたという。絶滅寸前だった高坂りんごの保存に尽力したのが、飯綱町のりんご農家、故・米澤稔秋さんだ。昭和62年(1987年)、稔秋さんは、高坂地区に残っていたわずか2本の高坂りんごから分けた苗木を自身の畑に植えた。腐乱病にかかり枯死寸前だった木から受け継いだ苗木は、植樹から約10年後、見事な実をつけるまでに成長した。
「親父は『高坂りんご』を地域の文化だと感じ、遺していかなければと思ったのだと思います」。息子の米澤紀之さんは、そう当時を振り返る。現在稔秋さんが遺した高坂りんごを受け継ぎ、栽培を続けている。
2005年、稔秋さんが植えた高坂りんごは牟礼村天然記念物(現在は飯綱町天然記念物)に指定された。しかし文化財として残すだけでなく、町の財産として広く活用していくことが大切だという考えを持っていた稔秋さんは、飯綱町とサンクゼールとともに、高坂りんごの経済的価値の創出のため模索を始めた。
「何か残していくための意味付けをしていかなければ、高坂りんごは再び廃れてしまう。町も、稔秋さんも、そう考えたのだと思います」(三浦さん)
飯綱町にしかないシードルをつくる

高坂りんごを使ったシードルを最初に醸造したのは、2008年のことだった。
「フランスのシードルメーカーを訪問したり、現地の人に話を聞いたりする中で、〝渋み・苦み〟のあるリンゴの必要性を私自身も感じていました。そうしたときに高坂りんごのことを知り、シードルで使ってみようという話になったのです」(三浦さん)
まずは町営の小さな加工所で高坂りんごのジュースを絞った。稔秋さんが収穫した高坂りんごを持ち込んでくれたときの姿を、三浦さんは今でも思い出すという。ジュースをタンクに入れサンクゼールに運び、醸造を開始。最初は高坂りんご100%のシードルをつくってみたが、糖の少ない高坂りんごではアルコール度数が高まらない。物足りなさがあったという。
「そこでふじをブレンドすることにしたのです。最初は8割ふじ、2割高坂りんごで醸造してみました。それだけでも単一品種で醸造するよりおいしいものができて、だんだん高坂りんごの比率を高めていき、現在は高坂りんご45%位の割合でつくっています」(三浦さん)
高坂りんごを使った「いいづなシードル」の最初の販売は2009年5月。本数は50本ほどしかなかったが、ソムリエや料理人など、食のプロに味を見てもらえる機会はあった。2年目、3年目と醸造を続けるうちに「本場フランスのシードルにも劣らない味」といった評価もされ、少しずつ知名度を上げていったという。
「いいづなシードル」の醸造を始めた頃、三浦さんは「高坂りんごのことを知ろう」と稔秋さんの自宅を訪ねたことがあったという。「高坂りんごの歴史や和りんごがどういうものなのか、島崎藤村が詠んだ『初恋』の林檎はもしかしたら高坂りんごのことだったのかもしれない……とか、いろいろな話を聞かせてくれました。席を立とうとしても、なかなか立てない位でしたね(笑)。そんな思い出があります」(三浦さん)
出来上がったシードルは必ず稔秋さんのもとへ届けに行ったという。シードルをつくり始めて3年ほどが経った頃、体調を崩した稔秋さんの入院先にまで届けたこともあったそうだ。入院先でも、リンゴの話題になると熱のこもった話をしてくれたという。 飯綱町内でしか売らないと決めたのも、稔秋さんとの話の中でのことだった。もともと高坂りんごは観賞するリンゴとして親しまれてきたものだ。景勝地としての歴史がある高坂りんごだからこそ、飯綱町に来て味わってもらうことが大事なのだという思いがあった。
リンゴの町のお酒と祈り

シードルづくりには苦労が多い。ブドウは足で踏めば簡単につぶれ果汁をとれるが、リンゴは一度クラッシュする手間がある。かつては重労働だったことだろう。加えてリンゴはブドウよりも酸が少なく腐りやすいため、ワインに比べアルコール発酵に失敗しやすい。もともとワインは水分を保存するためにつくられたものだといわれており、ヨーロッパでは水よりも多く飲まれてきた歴史がある。しかしシードルの産地であるノルマンディーやブルターニュは、冷涼な気候でフランスの中でも比較的雨量の多い地域だ。
「それでもこの地域の人たちがシードルづくりに挑んできたのは、ブドウの採れない地域でも『お酒を飲みたい』といった酔いへの欲求とか、『神様への祈り』とか、そういったものを求めた人々の思いがあったからではないかと私は感じています」(三浦さん)

お酒は古くから宗教的な意味合いのなかでも飲まれてきた。日本においてもそれは変わらない。米どころでもある飯綱町では、収穫の喜びを祝う秋祭りが各集落で行われ、五穀豊穣への祈りが毎年捧げられている。飯綱町で近代的なリンゴ栽培が盛んになったのは現代に入ってからのことだが、そうした地で「高坂りんご」が遺ってきたことも、それを使ったシードルが生まれたことも、必然的な出来事だったのかもしれない。 高坂りんごの栽培も徐々に広がっており、総出荷量も増加している。最初の醸造から10年が経ったいま、サンクゼールでは、高坂りんごに加え、さらに多くのリンゴをブレンドした新しいシードルづくりを計画しているという。2017年から蒸留を始めた、リンゴの蒸留酒「アップルブランデー」も順調に樽熟成を進めている。リンゴの町・飯綱町で、新しいシードル文化が根付き始めている。
※この記事は「産直コペルvol.38(2019年11月号)」に掲載されたものです。