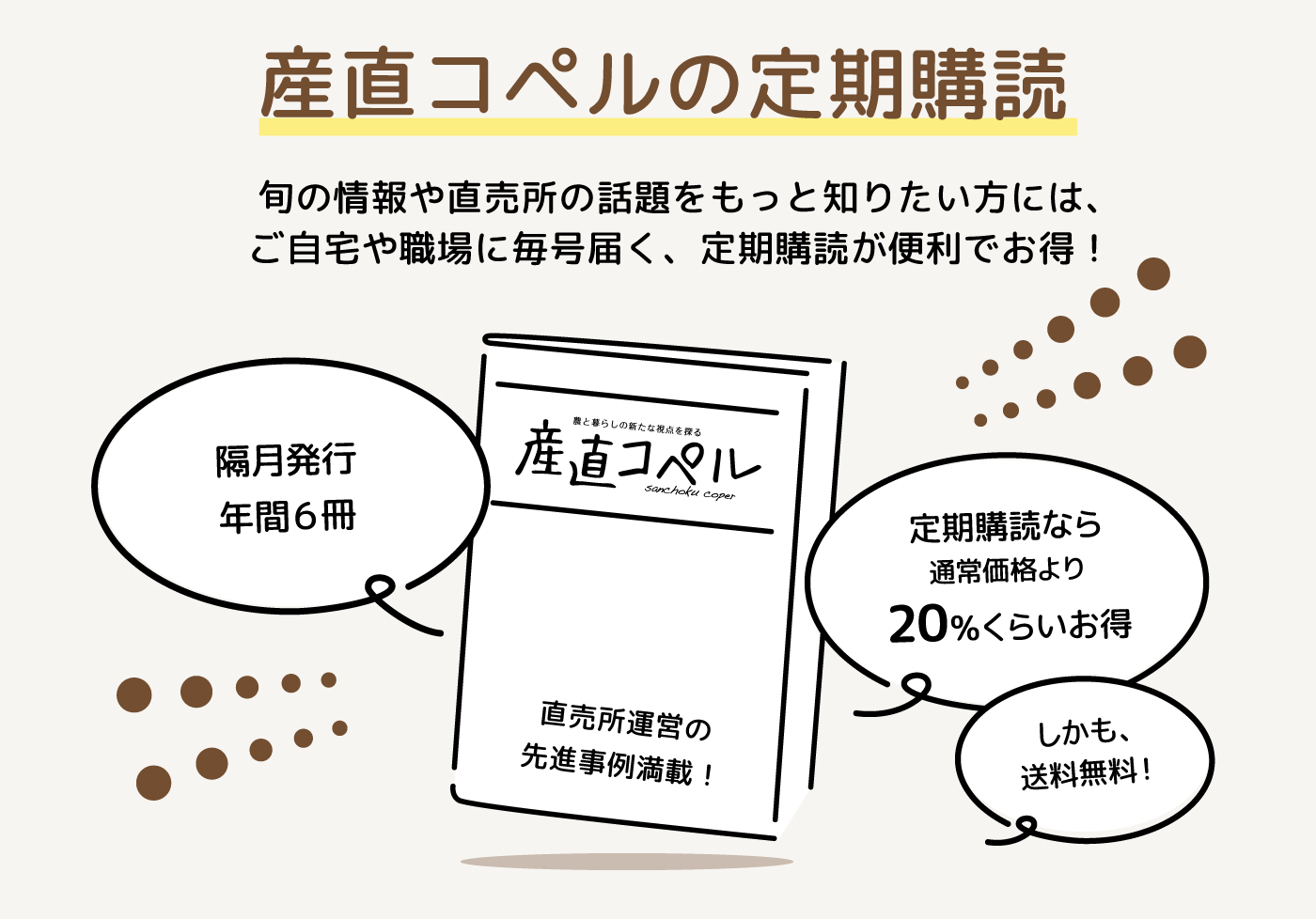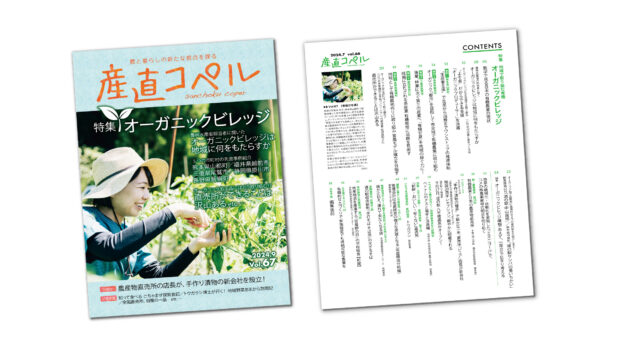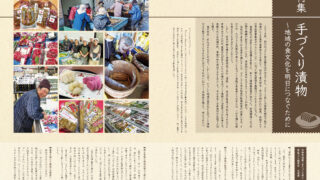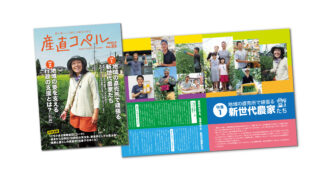直売事業は発生からおよそ30年を経て、いま、大きな転機を迎えている。施設の老朽化とその施設を使う運営者や生産者組織の高齢化を条件にして、施設リニューアルと経営体制の刷新が全国各地の直売所(特に道の駅併設型の店)で一挙に進められつつある。コロナ禍で“売れる店”と“売れない店”の違いが明確になったことも、こうした動きを加速する要因となっている。浮かび上がっている課題は何か? ここからどこに進むべきか? 巻頭の座談会での議論などを踏まえてまとめた。(『産直コペル』編集長 毛賀澤明宏)
押し寄せる 直売・地域を飲み込む大津波
コロナ禍の3年間を経て、全国の直売・地域づくりをめぐる状況は大きく変わろうとしている。
直売事業の運営組織の原点は組合運営方式であることはよく知られている。そこから組織を法人化するなどして事業規模を1億円以上に拡大させてきた直売所は、総じてコロナ禍でもある程度経営が安定していた。
しかし、そこまで至らないでいる数多くの直売所(売り上げ1億円未満の直売所は、全体の60%を占めるという統計値が出ている。都市農山漁村交流活性化機構 平成29年度実施アンケート)は、大半が経営危機に直面し、いま、全国的に広がる直売所再編の大津波に飲み込まれようとしている。
“大津波”とは端的に言って、直売所経営主体の大がかりな入れ替えの流れである。これまでのような農業や地域の振興を図る地元の運営団体、あるいは同趣旨で作られた地域企業(第3セクターも含む)、もしくはJAではなく、全国各地の道の駅をフランチャイズのようにして運営しようという新興「商業観光」会社や、同じく道の駅を集客力のあるアミューズメントスポットに仕立て上げ周辺地域の開発で利益を上げようとしているかに見える不動産事業者、およびそれらを支える大手コンサルタント会社や銀行などがスクラムを組むかのようにして、この大再編に乗り出している。これに様々な異業種・他産業の大手企業が参画している場合も多い。
このような動きが顕在化した直接的な要因は、政府が「地方創生」政策を掲げて道の駅などを拠点とした地域活性化に手厚い支援を用意していることがある。
他方で、このような政府の動きに対応して、地域独自にそうした支援策を受け入れ創造的に展開できる力が低下していることもある。特に、道の駅併設の直売所や立ち寄り湯などを運営する第3セクターの「赤字体質」に苛まれてきた地方自治体の中には、「赤字しか生まない地域の会社」よりも、運営力・集客力・組織力が優れているかのように見える「大きな」「外の組織」に事業を委ねた方が得策と判断するところも少なくない。
かくして老朽化した施設のリニューアルと同時に、運営組織そのものを「外部の会社」にすげ変えてしまう事態が多く発生しているわけなのだ。道の駅の併設施設にテナントとして入居して(有償の場合も無償の場合もある)直売事業を展開していたような団体は、そこで展開していた「直売事業」の運営権を「無償譲渡」するように迫られ、直売事業の経営・運営主体から「外されて」いこうとしているのである。
 豪雪地帯の新潟上越の直売所に並んだ豊富な地元産野菜(1月)。
豪雪地帯の新潟上越の直売所に並んだ豊富な地元産野菜(1月)。 JAえちご上越が運営する旬彩交流館 あるるん畑(新潟県上越市)にて
原点は、農家の収益増・地域農業の活性化
この動きにどういう対応をするべきか? まずは直売事業の原点を再確認しよう。
直売事業の原点は、生産農家の手取り収入の増大のための共同販売の場であった。系統出荷しか販路を持たなかった農家が、はじめは系統出荷では扱ってくれない規格外品を持ち寄り、徐々に消費者に歓迎される新鮮で美味しい・なおかつ安全で安心な農産物を集めるようになって販売収入を得た。それは流通過程での中間マージンや運送経費がかからないが故に、消費者にとっては一般の小売業の店で買うよりも安く、生産者にとっては系統出荷に比べて手取り収入率の高い、優れた流通・販売の仕組みだったといえる。
そればかりではない。出荷する生産農家はこの直売事業に主体的に参加することを通じて、消費者の反応を直接耳にして学び、仲間の生産者と切磋琢磨して技術や知見を高め、地域の農業集落の中心的担い手として成長した。年をとってもいつまでも働ける場を手に入れ、健康増進にもつながる社会的効果もあった。また、販売業務や加工事業など農村における雇用の場を創出することにもなった。
このように、農産物直売事業は、地域の農家やそれに連携する様々な人々が主体となって地域を作り出していく、多面的な機能を持った地域創造の事業だったのだ。
もちろん出発点ではそのような性格を有していた直売所も、発生以来30年を超える歴史の中で、様々な発展と変容を重ねてきた。しかし、忘れてはならない原点は、ここにある。
では、いま、各地で直売所を飲み込もうとしている大津波は、このような直売所の原点を現在において創造的に発展させるものであるのか?
事業の運営主体は誰なのか? そこであげられる収益は誰によってどのように分配されるのか? 運営者と出荷生産者との関係はどのような形になるのか? 地域に還元されるものは何なのか? それは地域にとってどのような「発展」をもたらすのか?……さまざまな視点から吟味して見ると、現在生起している〝大津波〟は、直売事業の原点からは相当かけ離れたものであるように思えてならない。
 レシピがずらりと並ぶのも直売所ならでは。
レシピがずらりと並ぶのも直売所ならでは。JAえちご上越 旬彩交流館 あるるん畑(新潟県上越市)にて
地産地消―農業生産を軸にした地域活性化を
では、現在、どのような切り口からその発展方向を考察すれば良いのか?まず第一は、直売事業発生の原点に立ち返って、地域の農業振興を事業の基底にすえることであろう。大量生産・大量消費が可能な平地の農業地域においても、人口減少・農家の高齢化・遊休農地の拡大など山積する課題に直面している中山間地の農業集落においても、等しくこのことがまず問われなければならない。
もちろん、そこで展開される農業の規模や形、それを担う組織や人々の在り方、品目や栽培方法などは多種多様である。地域としては単品作物の大きな規模の産地形成を目指しつつ、その出荷物の一部を地域の直売所に集めるという形もあるだろうし、従来直売所が得意としてきた中小規模の多品目生産者が創意工夫して豊かな出荷物をそろえるという形態もあることであろう。環境に負荷の少ない有機無農薬農法や減農薬農法などを採用するかどうかも検討する必要があるだろう。大型農家を継承する専業農家の育成に軸を置くか、いわゆる「農ある暮らし」を求めて移住してくる新たな担い手たちが働きやすい環境を作るか…選択肢は多岐にわたるけれども、その地域に継続可能な形の農業を育て定着させることが、直売事業の基底に置かれるべきテーマであることは間違いない。
あくまでも、当該地域で当該地域の人々が当該地域の有効資源を活用した商品(農産物・農産物加工品)を生み出し、これを地域の人々の力を集める形で販売していく「地産地消」の原則が貫かれるべきなのである。
道の駅の施設リニューアルにあたってよく耳にする「集客力がある道の駅を作れば、農産物も売れるようになり、地域の農家も潤う」というロジックについて付言する。農産物が売れなければ農家が潤わないのはその通りである。しかし、直売事業の現場が直面している問題は、現状では売るもの、つまり地場産農産物が払底しており、およそ昼過ぎごろには底をついてしまうのが常である。この根本問題の解決が喫緊の課題になっている。地場の生産力を上げ、それを直売所に集める集荷力を高めなければならない。この問題と正面から向き合わずに、「売れるものが足りなければ、市場に注文を入れれば良い」というような安易な発想に陥っている人だけが、「人が集まる施設を作れば農産物が売れる」などという宙に浮いた絵空事を並べたてることができるのではなかろうか?
 「直売所は地域の重要な就労場所になっています」と話す産直あぐり(山形県鶴岡市)の鈴木光秀社長(右)
「直売所は地域の重要な就労場所になっています」と話す産直あぐり(山形県鶴岡市)の鈴木光秀社長(右)直売所の販売力強化・経営力の引き上げを
だが、「集客力のある道の駅を作れば、農産物が売れる」というロジックがまかり通ってしまうのには、現在の直売事業の側にも要因がある。端的に言って、客も少ないし、販売高も大したことがない―という直売所が、残念ながらそれなりの数、存在しているという厳然たる事実があるのだ。
先にも述べたように、売り上げ規模が1億円に達していないような直売所では、販売力は年々下落しており、経営もおぼつかない店が多い。ここを突破すること。つまり直売所の販売力強化・経営力の引き上げが、第二の切り口であろう。
もちろん例外はあるとは言え、売上額が1億円に満たない直売所、5000万円から7000万円あたりで停滞している直売所の多くが、誰が作る、何を、いつ、いくつ売ってどれだけの売り上げにするかーという販売目標・販売計画が作られていない。あるいはせいぜい、売り上げの数字目標を設定することでそれに取って代えたりしている。高額なPOSレジシステムを導入し、その中には販売計画づくりに役に立つ機能が満載されているにもかかわらず、それらはほとんど活用されたことがないのである。例えば、売上計画づくりの核心となる「品目ごとの売上状況」を掌握したことはないという店は、売上額が1億円未満の店の6~7割を占めるのではないかと思われる。
この、販売状況を数値化してとらえ合理的な販売計画を立てることができないという問題は、単に清算・経理上の問題としてだけでなく、店=経営者・運営者と、出荷生産者との関係作りなどにおいても、合理性や計画性を欠いた場当たり的なものになってしまうなどの悪影響となって表れてもいる。
直売所は、元々は生産者が思い思いに栽培したものを持ち寄り、それを共同して売り、しっかり清算するという仕事で成り立ってきた。だが、そこから一歩飛躍して、モノを売る業としての事業を展開できるようにならないと、次のステージには進めないということであろう。
 地元企業の若手社長らが作った地域づくり会社「海山社中」が運営する道の駅くしま(宮崎県串間市)の直売所。中央が立本与司仁副社長
地元企業の若手社長らが作った地域づくり会社「海山社中」が運営する道の駅くしま(宮崎県串間市)の直売所。中央が立本与司仁副社長直売所や規則や決まり事の現在的見直しを
右に述べた合理的な販売計画の策定とそれに基づく運営改善・経営改善とも関連して、手を付けなければいけないこと、切り口の第三は、発生から30年間にわたり、いわば直売所の当然のしきたり・おきてのようにして守られてきた規則や決まり事の現在的見直しである。
例えば、直売所では、自分の出荷物は自分で梱包して、自分で搬送して出荷するというのが、〝当たり前〟の規則として実施されてきた。しかし、従来直売所の主要な出荷者層であった比較的高齢の中小規模の農家の出荷品だけでは品不足となっている現実を鑑みると、若手の大きな農家からの出荷も呼び込んでいく必要がある。その時に、自家梱包・自己搬送といったこれまでの決まりでは、逆に足かせになってしまうという指摘は全国から上がっている。系統や市場出荷と同じように、ケースやラックに入れたまま出してもらい、パッケージラベル貼りなどは、店側が手数料をもらって代行するというシステムを現実的に導入している店もかなり生まれてきている。
この他にも、出荷・荷下時間の設定や、売れ残り品の扱い方、棚の利用方法、当番制の在り方、そもそも手数料の在り方を含めて、現在的に吟味し、変えるべきものは変えていくことが必要であろう。
以上、紙幅の都合もあり、詳細は割愛せざるを得なかったが、1地域農業の振興を事業の基底に置くべきこと、2データなどを活用した販売力強化・経営力向上、3時代遅れの規則や決まり事の見直し・再検討の3点を、現在の直売事業のステージアップに必要な切り口として挙げた。問題提起として、ぜひ検討していただきたい。
※掲載の写真はすべてイメージです。本文とは直接関係ありません
 JAが地域農業の拠点として設置運営するええじゃん尾道(広島県尾道市)
JAが地域農業の拠点として設置運営するええじゃん尾道(広島県尾道市)
※この記事は「産直コペルvol.60(2023年7月号)」に記載されたものです。