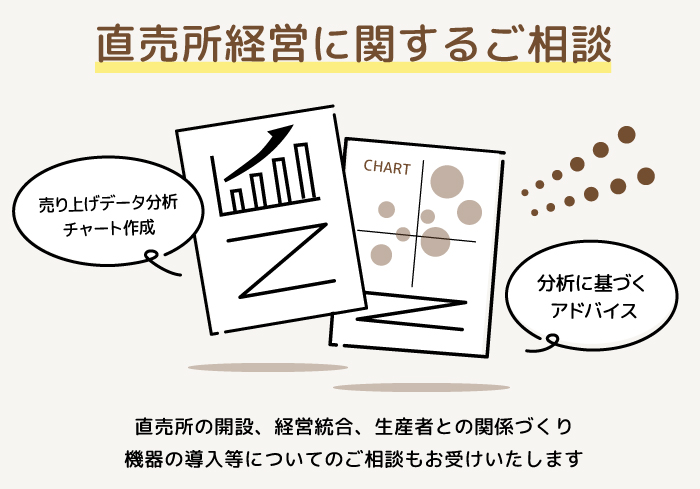文・森岡亜紀(全国農産物ネットワーク)

「伝統野菜」と「在来作物」の違い
山形県鶴岡市で開催した今年の「全国農林水産物直売サミット」では、分科会のテーマの一つを「直売所から伝える、在来作物と食文化」とした。「伝統野菜」ではなく「在来作物」としたのは、講師の山形大学農学部江頭宏昌教授の考えを踏まえている。
一般的に「伝統野菜」とは、各地の生産・流通団体がその産物のブランド化を目指し、一定の基準を設けるなど、定義を明確にしている場合が多い。一方、「在来作物」は、「伝統野菜」も含め、「地域において世代を超えて自家採取などを通じて栽培され、地域住民の生活に利用されてきた作物」と、よりゆるやかな定義である。これには野菜だけではなく、地域の暮らしの中で受け継がれてきた果樹、穀物、豆類、鑑賞・染料・薬用作物なども含まれている。
「ラ・フランス」も元は「在来品種」
山形の直売所は「在来作物」とその加工品や料理の宝庫だ。「山形在来作物研究会」によれば、現在179種類の在来作物がある。そこに山菜・果樹・きのこや新顔野菜なども加わり、直売所は多品種の農産物の見本市のような品揃えだ。
今では全国に流通する「佐藤錦」(サクランボ)、「ラ・フランス」(西洋梨)、「だだちゃ豆」(枝豆)、「もってのほか」(紫の食用菊)も元は「在来作物」だ。山形の産地で受け継がれてきたそれらの価値が対外的にも評価され、名実ともに全国区になっていった。
暮らしの中に根付く「在来品種」
山形県民の意識の中で、「在来作物」は特別なものではない。秋になれば「山形せいさい青菜」の「せいさい青菜漬」や「おみ漬」を家庭で漬け込み、「蔵王かぼちゃ」(外皮が白くて硬く日持ちする)や「悪戸いも」(ねっとりした里芋)を煮こみ、在来の大根や大豆を長く保存して冬場の食事に備えるのが長く受け継がれてきた当たり前の暮らしだ。そして、これを支えているのが各地の生産者や直売所である。
「在来品種」は地域の目玉になる
「在来作物」は多品種少量販売を特色とする直売所とは相性が良い。出荷時期が限られ、希少価値の高い作物は、店まで足を運んでもらうきっかけにもなる。
滋賀県米原市の「道の駅伊吹の里・旬彩の森」は、下火になりかけていた「伊吹大根」(ねずみ大根)や「赤丸かぶ」の生産振興の旗振り役となり、関連商品の開発までを手掛けている。
福島県玉川村の「道の駅たまかわ・こぶしの里」は、地域に元々あった「さるなし」(コクワ)に目を付け、産地形成を図り、商品化し、全国さるなしサミットの開催など、さるなし産地交流の中心役になっている。
大阪府河南町の「道の駅かなん」は、「田辺大根」や「毛馬胡瓜」など「なにわ伝統野菜」が揃う店として、地元の料理人などからの信頼が厚い。
「在来作物」は直売所の売りになるだけではなく、地域全体の目玉となり、全国的な注目を集めることにもつながっている。

かつては「新顔野菜」だった「在来作物」
「在来作物」の各地での起こりを見てみると、「大名のお国替えで種が持ち込まれた」、「旅行者が親切にされた礼に種を分けてくれた」、「お伊勢参り道中で買い求めた」、「嫁入り時に親から渡された」など、人の動きとともに種子も移動し、その土地に根付いたとされていることも多い。
また、日本各地に在来種があるナスは奈良時代に中国方面から、キャベツは江戸後期にヨーロッパから日本に持ち込まれているように、かつての「新顔野菜」が地域で受け継がれ、風土に育まれて「在来作物」として定着していることもわかる。
直売所があるからできるトライ&エラー
過去から受け継いだ「在来作物」と、未来の主力となりうる「新顔作物」の双方にアンテナを張った品揃えや生産振興は、直売所の得意とするところだ。「在来作物」の産地を支え、その価値を伝える一方で、土壌条件や気象変動にも対応した、消費者にとっては目新しい「新顔作物」の紹介も進めていく。商品の作り手が挑戦と模索を繰り返して出来るのも、安心して商品を託せる直売所が近くにあることが大きい。
※この記事は「産直コペルvol.39(2020年1月号)」に掲載されたものです。